あなたは何を頼りに生きていますか? と問われたら「自分の感覚です」と誰もが答えるでしょう。それ以外の答えの人っていますでしょうか? いないだろうと言う前提で話を進めますが、ここ最近これを「科学」に統一しようと言う圧力が社会的に強まっているように思います。
しかし、これは非常に愚かな行為です。なぜなら、私が聞いたところによると、科学は何も知らない、らしいのですから。


あなたは何を頼りに生きていますか? と問われたら「自分の感覚です」と誰もが答えるでしょう。それ以外の答えの人っていますでしょうか? いないだろうと言う前提で話を進めますが、ここ最近これを「科学」に統一しようと言う圧力が社会的に強まっているように思います。
しかし、これは非常に愚かな行為です。なぜなら、私が聞いたところによると、科学は何も知らない、らしいのですから。
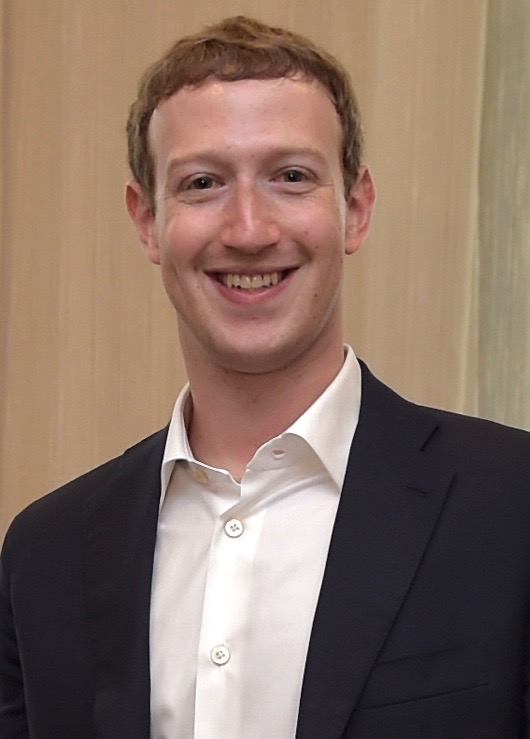
みなさん、ベーシックインカムって知っていますか? 私も最近知ったのですが、ちょっと気になって調べてみたんです。と言うのも、この制度、私達庶民の未来の生活に非常に大きな影響を持ちそうなのです。
ちなみに、ウィキペディアには、
国民の最低限度の生活を保障するため、国民一人一人に現金を給付するという政策構想
と記されています。「え?ただでお金がもらえるの? そんな馬鹿な話はないでしょ」いえ、必ずしもそうとは言えません。なぜなら、
「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
と日本国憲法に定められているからです。
このただでお金をもらえるという夢のような制度、実際に導入が真剣に検討され、欧州などで実験も行われているようです。こんな素晴らしい仕組みは、早く取り入れてほしい、と思うでしょうか? それとも、怪しい話、うまく行くはずがないと?
実は、この夢の制度の「いい?悪い?可能?不可能?」の判断に、難しい議論は、まったく必要なく、いとも簡単に答えを導き出すことが出来ると私は思っているのですが・・。

最近、人工知能やロボットに関する話題が多くなってきましたね。囲碁や将棋の世界では、A.I.は圧倒的に人間を凌駕するまでに進化してきました。さて、そんな人工知能が進化した未来について、「恐ろしい」という人がいる一方、「ロボットの発展によって、みんなが幸せになれる社会がやってくる」と考える人がいるようです。そして、そんな見解を主張する記事なども増えてきたように思います。
当ブログでは、ロボットや人工知能に関して、ほとんど独自と言っていい、他とは一線を画す捉え方を提唱してきたつもりです。そして、今回のテーマに関する考え方は、記事名ですでに分かると思いますが、残念ながら、非常にネガティブです。「ロボットが運ぶみんな幸せな社会」は、単なるまやかしに過ぎないことは、ここでお伝えしてきた内容をまとめれば、簡単に分かってしまう気がしているのです。

少々、記事のタイミングを逸した感がありますが、とうとうplayStasionVRが発売となり、これから活況となることが期待されるVR市場。株式市場にもこれに期待した買いが入っているようです。対して、先日発表になった「NX」こと任天堂の新ハード「Switch」ですが、それに対する株式市場の反応は暴落でした。
投資家の視点を侮ってはいけません。ここから考えるにソニーの勝利、任天堂の敗北はもはや決したようなもの、そう考えるのは自然なことなるでしょう。しかし、ちょっとだけお時間をください。投資家がどれだけ任天堂に失望をくらわせようとも、それでも当ブログでは任天堂を応援するに足りる重要な理由があると思っています。
それに成功間違いなしかのようなVRですが、しかし果たして、これとて本当に流行るのでしょうか? 私から言わせると、それは極めて自然な理由から流行らないのでは? と思えるのですが・・。

最近、人工知能関連のニュースを見る機会が多くなりましたね。当ブログでは未知なる人工知能に対する捉え方を考察し、なかなか本質的なところをお伝え出来たつもりになっているのですが、それに同意いただけるかはともかくとして、少なくとも科学者の言っていることは話半分に聞いた方がいいです。専門家の言っていることが一番正しいはず? いえいえ、だってそれを作っている彼らがその悪いところを大っぴらに語るはずがないではありませんか。著名な科学者だろうとそれは人の常です。
彼らはハイリスクハイリターンのハイリスクを本当には語りたがりません。だから、私たちは彼らの言葉など鵜呑みにせず、自分たちで考える必要があるのです。それともハイリスクはないと思っている方がいたとしたら、それは科学に恋をしすぎです。ハイリスクハイリターンは誰もが知っている眼前たる事実です。
「人工知能が最適な選択をしてくれる時代になる」そんなことをよく聞きますが、それは逆に自分で考えることの大切さが今まで以上に重要になることを意味していると言えるでしょう。
私は私の最適を人工知能などに決められたくはないのです。私にとって最適だったものは、人工知能に決められた時点で最適ではなくなるのです。それが私の価値観だからです。

最近、人工知能関連のニュースが増えてきてます。当ブログでもたびたび取り上げ、その捉え方に於いて、一線を画したお伝えが出来たかなあと自負しているところです。引き続きこのテーマを取り上げていきたいと思うのですが、今回は、「人工知能、ロボットが感情、こころを持つことはあるのか?」という問いを考えてみたいと思います。
これに関して、私は正直なところ、非常に馬鹿げていると考えていると言うことをまず記したいと思います。科学者がそういうものを造ってみたい、という心理は理解出来ないことはないですし、”いつかは”造られる可能性があるかも、とは思います。しかし、フィクションでみるように、こころを持ったロボットが街中に溢れると言うような未来は決してやってこないでしょう。なぜなら、それは無意味だからです。
ロボットに感情を持たせることは無意味です。断言します。せいぜい、「心に似せた都合のよいもの」を搭載した人工知能くらいじゃないでしょうか。それは所謂偽物です。本物のこころは相当遠い未来の発展の先に一瞬、芽生える可能性はありますが、その持続は決して不可能ではないか、と思います。
それを考えるには、「感情、こころ」とは何か、と言うことを捉えなくてはならないと思いますが、それは余りにも難しい問いなので、今回はやめておきましょう。別の機会があればと思いますが、その時にも当ブログの「合理性と非合理性の仮説」がきっと役に立つはずです。では、今回はどうするかと言うと、フィクションを創って、思考シミュレーションをしてみたいと思います。それでもその難解な私たちのこころの一端を掴むことが出来るかもしれません。
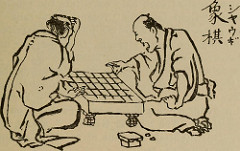
プロ将棋界のカリスマ、「羽生善治」さんが、とうとう人工知能と対戦するかも、と言う話が出ているそうです。当ブログでは、人工知能関連ニュースを取り上げ、その中でAIに関する捉え方と、その崇拝の危険性をお伝えしてきました。
私が、羽生善治さんが人工知能とは対戦しない方がいいと考える理由は2つあります。それはもし、羽生さんが敗北してしまったときに、「プロ将棋の価値の崩壊」を招く可能性があること、そして、「AIへの崇拝が進んでしまうこと」の2点です。もちろん、羽生さんが勝利すれば、この心配はしぼんで、むしろいい効果を得られるかもしれませんが、どちらにしろ、いずれ敗北を喫することは明白だと考えるからです。

こんな記事が出てました。当ブログでは、予てから人工知能と言う科学技術への捉え方について、色々と記してきましたが、この記事に書かれている通り、その進化は、私たちの格差を広げることは間違いがないと考えられます。なぜなら、それが、人工知能、科学の本質だからです。
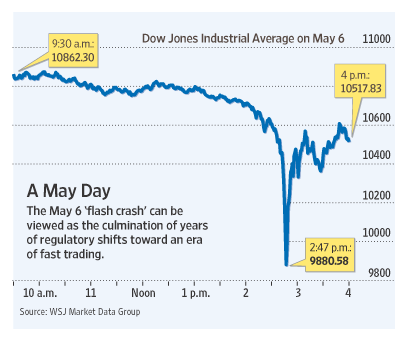
少し前の話ですが、マーケットにおける人工知能を駆使した「ロボット・トレーディング」、超高速取引を規制する方向で検討に入ると伝わりました。超高速取引とは、1000分の1秒単位で取引を繰り返す投資手法で、それを操るのは、最新のAIを搭載したコンピューターです。
世界的には、マーケットを荒らす要因、また公平性を欠く取引だとして、嫌われ、規制の方向にあるようですが、そんな中、日本政府はこれまで、これを容認、野放しにしてきたのようですが、なぜこのタイミングでそんな声が出始めたのでしょうか。その理由には、公平な取引のためとか、個人投資家を守るためとかの、恰好いい理由ではなく、単に日本政府の都合と言う部分がありそうです。
それは日経平均株価の現在の位置ではないでしょうか。

今回は少々重大なテーマについて書いてみたいと思います。最近、人工知能関連ニュースを耳にすることが多くなってきたのですが、それらを聞いていていて、私が非常に危惧を感じるのは、人工知能というその技術そのものよりも、それに対する人のとらえ方です。
「人工知能は人間を超える」
「人が敗北する時代が来る」
そんな声が非常に多く、ネットにも溢れていますが、これはA.I.技術に対する恐れを通り越して、畏れ、さらに言うとほとんど崇拝になってしまっています。
この捉え方は、非常に偏屈な視野の狭い見方であり、非常に危険であると断言せざるを得ないでしょう。まあ、科学に対する崇拝は世の常ではあるのですが、本当は人工知能とは単にハイリスク・ハイリターンの道具であり、原発と同じような性質のものだと言うことです。現時点で、これから先の未来においても(永久にかはわかりませんが)、A.I.が人間の脳を超えることなど100パーセントあり得ません!
その理由をこれから詳しく書いていきますが、この記事は私のブログの中でも重要度は結構高いです。きっと最後まで読んで頂ければ、納得、共感頂けると信じております。人によってはパナマ文書より衝撃の内容となるでしょう!(笑)。
Powered by WordPress & Theme by Anders Norén
© 2010 文学的未来表現