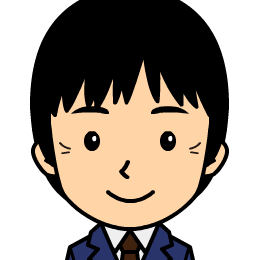またしても文学的な作品です。
これは大学時代に呼んで衝撃を受けました。やっぱり、古いものは時代が選んでいるので、優れたものが多いんです。今現代の物でもいいのたくさんあるのでしょうが、やはり、文学といわれるものは、何百年という時代の淘汰に耐えた作品たちです。今現在の作品とはふるいのかけられ方が違います。やはり、外れを引くこともないし、強烈なのものが多いのは当然といえます。
その中でも、これはどっちかというとマニアックでしょうか。志賀直哉の作品ですが。とても短いので、是非読んでいただければと思います。
あらすじ
范という若い支那人の奇術師が演芸中に出刃庖丁ほどのナイフでその妻の頸動脈を切断したという不意な出来事が起った。若い妻はその場で死んでしまった。范はすぐ捕えられた。
現場は座長も、助手の支那人も、口上言いも、なお三百人余りの観客も見ていた。観客席の端に一段高く椅子をかまえて一人の巡査も見ていたのである。ところがこの事件はこれほど大勢の視線の中心に行われたことでありながら、それが故意の業か、過ちの出来事か、全くわからなくなってしまった。
その演芸は戸板ぐらいの大きさの厚い板の前に女を立たせておいて二間ほど離れたところから出刃庖丁ほどの大きなナイフをかけ声とともに二寸と離れない距離にからだに輪廓をとるように何本も何本も打ち込んで行く、そういう芸である。
裁判官は座長に質問した。
「あの演芸は全体むずかしいものなのか?」
「いいえ、熟練のできた者には、あれはさほどむずかしい芸ではありません。ただ、あれを演ずるにはいつも健全な、そして緊張した気分を持っていなければならないということはあります」
テーマとなる意識と無意識の境界とは?
過失と殺人の差はどこにあるかというと、本人にその意図があったかどうか、ということになりますね。言葉は悪いですが、そんなつもりないのに、うっかり殺してしまったのが、過失致死。殺人は言うまでもなく、殺そうとして殺すことです。これらは、どちらも犯罪ですが、しかし、その罪の大きさには雲泥の開きがあるように思います。
これは、では過失に見せかけた殺人かどうかを問う作品かというと、そんな凡庸なものではありません。それがこの小説のテーマですが、この小説の特異なところはそれが「本人にも分からない」というところにあります。つまり、自分がわざとやったのか、それとも、手が滑っただけなのか、分からないというんです。そんなことがある? と思いますが。人間の意識と無意識の境界の微妙な領域を志賀直哉はついてきています。実際、人間の意識なんてこんなものですよね。
范は裁判で、女房を故意に殺すような動機がまったくないわけではないといっています。そういった夫婦の揉め事があったことを認めています。しかし、本当に確信してわざと狙ったのかというと、そうでもないと。彼にはわからないのです。最後に裁判長は自分のノートに無罪と書き込むところで話は終わっています。
無罪の理由は・・
過失にしろ、実際無罪ではなさそうです。しかし、范が嘘を言っていないこと、人間は自らの意識を100%知覚することなどできないこと、この状態には罪を問えないこと、を印象付けるために「無罪を与える」という結末を志賀直哉は選んだのではないでしょうか。
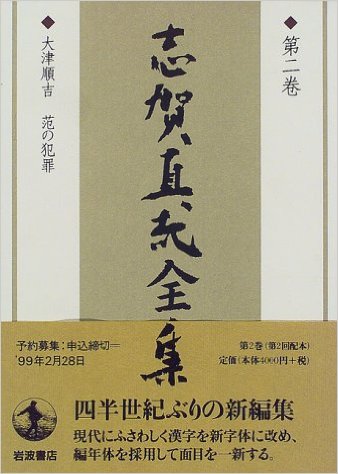
-150x150.jpg)